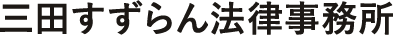よくあるご質問
法律相談に関するご質問
Q:どのような内容なら相談して良いのでしょうか?
どのようなことでも構いません。 法的な問題かどうか、法的にどのような解決方法をとれるかなどはお話を伺ったうえで判断し、ご案内いたしますので安心してご相談ください。
Q:メールや電話で相談はできますか?
恐れ入りますが、原則として面談での相談をお願いしております。ただし、緊急性のある事件(DVを受けた、別居させられた、子を連れ去られた、裁判所や弁護士から手紙が来ている、相手方から近々の対応を求められている、逮捕された、自首したい、今すぐ契約して弁護士に動いてもらいたい、など)については、お電話をいただければ原則、即日の対応をいたします。 相談希望の場合、メールフォーム(お問い合わせページへリンク)やお電話からご予約をいただけますと幸いです。
Q:子連れでも大丈夫ですか?
はい、当事務所はキッズスペースも完備しておりますので、お子様とご一緒でも大丈夫です。面談の予約時にお申し付けください。
Q:相談予約はどのようにしたら良いでしょうか?
メールであればこちらから、お電話であれば下記へおかけください。
TEL079-599-7350(24時間電話受付)
Q:相談したら必ず依頼しないといけませんか?
いえ、そのようなことはありません。 相談だけでも問題ありませんので、気になることがあればご相談ください。
Q:駐車場はありますか?
はい、敷地内の無料駐車場(事務所ビル敷地内7番・8番ほか複数台駐車可能)がございますので、そちらをご利用ください。面談時や打ち合わせなど、ご来所の機会にご利用いただけます。法律事務所を決める際、毎回かかる駐車場代金は盲点だったと後悔される方は多いです。
Q:土日や夜でも相談は可能ですか?
はい、土日や夜間などでも相談可能です。緊急性のある事件(DVを受けた、別居させられた、子を連れ去られた、裁判所や弁護士から手紙が来ている、相手方から近々の対応を求められている、逮捕された、自首したい、今すぐ契約して弁護士に動いてもらいたい、など)については、原則、即日の対応をいたします。 24時間お電話を受け付けておりますので、緊急性が高い事案の場合はその旨をご連絡ください。
Q:相談にあたって準備すべきものはありますか?
必須というものはありませんが、問題についての証拠や状況をまとめたメモなどがあれば相談がスムーズになります。 また、即時ご依頼いただく場合、ご契約のため印鑑が必要となります。
ご依頼に関するご質問
Q:依頼後は裁判所へ行く必要はありますか?
基本的には弁護士が代理人として出廷しますので、全ての手続きにおいてご依頼者様が裁判所へ出廷いただく必要はありません。 しかし、本人尋問や証人、家庭裁判所での手続きなど、出廷が必要な場合はございます。 また、刑事事件の被告の場合は原則必須となります。
Q:依頼後に事務所へ伺う必要はありますか?
状況報告や費用の清算など、必要に応じてご来所をお願いする場合がございます。
Q:費用はどのタイミングで支払えば良いですか?
事案によって異なる場合はあるので、下記のタイミングとなります。
- 相談料:相談後にお支払いいただきます
- 着手金:ご依頼時点でお支払いいただきます
- 報酬金・実費等:問題解決後にお支払いいただきます。
費用について詳しくは弁護士費用ページをご覧ください
Q:依頼から解決までの期間はどのくらいですか?
問題により異なりますので、期間を一概に申し上げにくいですが、ご相談の際に経験からの目安をお伝えすることが可能です。
Q:家族に知られずに依頼することは可能ですか?
弁護士には守秘義務がございますので、当事務所からご家族方に依頼状況をお伝えすることはありません。また、ご連絡先や郵送物などについては最大限配慮いたします。
離婚・男女問題について
Q:調停は裁判と違って話合いの場で、調停員もいますから自分でできますよね?
できないと思います。 調停員は中立な立場であり、片方に有利になるような助言などはしません。そして、調停員は、さりげない会話の中で、法律的に意味のある事実を拾っていき、証拠の提出を求め、その結果をまとめた調停報告書を作っていきます。気づいた頃には、重要な事実は証拠とともに固まってしまい、動かせなくなってしまいます。これを防ぐためには、調停のルール(家事事件手続法等)を熟知した上で、家事に関する法律(民法等)に精通し、調停員の質問があるたび、その法律的意義を即座に理解し、その場で適切に回答する必要があります。そのようなことが一般の方にできるとは到底思えません。
Q:相手方は離婚に合意しており、あとの交渉は自分でもできますよね?
難しいと思います。 離婚条件は、離婚の時期、方法、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金と非常に多岐にわたります。離婚において、最大限有利な結果を得ようとすれば、相手方と交渉する際に上記一つ一つについて正確な法律知識を有した上で交渉に臨まなければならず、それは、交渉技術に長けていないことも相まって、一般の方には大変難しいものと思います。 上記の情報を信じた結果、ウン十万円、時にはウン百万円の損をした方を非常に多くみてまいりました。離婚等家事事件は、法律的知識をはじめ、裁判、調停実務に精通し、交渉の技術及び数多の交渉経験を有する弁護士に依頼することが最善の方法であると考えます。 なお、先に掲げた家事事件手続法の知識、調停や裁判実務、交渉の技術は司法試験(法曹になるための試験)の試験科目にありません。そこで、もっぱら実務での研鑽によるほかないというのが現状です。そこで、家事事件は豊富な経験を有する弁護士を探すことがより一層大切であると言えるでしょう。 この点、離婚等家事事件に高い専門性を有し、解決事案の豊富な当事務所をお選びいただくメリットは計り知れません。
相続問題について
Q:遺言書は自分でもかけるのに、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか?
自筆でも遺言書を作成することは可能ですが、内容に不備があったり、法律上無効になるリスクがあります。また、相続人間での争いを防ぐためには、法的に有効で明確な遺言が必要です。弁護士に依頼することで、相続関係の整理や適切な文言の選定など、将来のトラブルを回避するためのサポートを受けることができます。
Q:遺産相続に期限はあるのでしょうか?
はい、相続にはいくつかの期限があります。たとえば、相続の放棄や限定承認は、相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。また、相続税の申告・納付は、相続開始から10か月以内と定められています。期限を過ぎると不利益を被ることがありますので、早めの相談が重要です。
刑事事件について
Q:国選弁護人がいるのに私選弁護人に依頼するメリットはなんでしょうか?
国選弁護人も弁護士ですが、選任は裁判所が行うため、本人が選ぶことはできません。私選弁護人であれば、依頼者との信頼関係を築いたうえで、よりきめ細かく、柔軟な対応が可能です。また、早期からの対応や面会、証拠収集に積極的に動くことができる点もメリットです。
Q:逮捕されるかもしれないのですが、このタイミングで依頼はできるのでしょうか?
はい、逮捕前の段階でも弁護士に依頼することは可能です。事前に弁護士が状況を把握し、警察への対応方法や取り調べへの備えをアドバイスすることで、不必要な混乱を避けることができます。逮捕後の早期対応にもつながるため、できるだけ早いご相談をおすすめします。
借金・債務整理について
Q:借金の整理は、定型的なものだからどの弁護士に依頼しても同じではないでしょうか?
弁護士の選定は非常に重要です 債務整理のうち、任意整理は債権者との交渉になります。交渉における知見がモノを言う場面そのものです。また、再生及び破産は、申立方法や裁判所への説得の巧拙により、依頼者の不利益が大幅に左右されるため、解決数(経験)が非常に重要です。また、多くの弁護士は借金問題を敬遠しがちです。それは、手間がかかること、誠実でない依頼者が多い、などの理由からです。きっと、弁護士自身、お金に困った経験がなく、借金問題がいかに人生において大きな暗雲を垂れ込ませるものなのか分からないのでしょう。
Q:破産や再生などは、今後の人生に影響が大きいと思うのですが
誤解による思いこみの場合が多いです 破産すれば家族や親類すべてに知れ渡る、カードやローンが一生利用できない、すべての財産を失う、職を失い再就職が難しい、選挙権がなくなる、などはすべて誤っているといえるでしょう。膨れ上がった借金がなくなり、返済の毎日から脱却できるメリットは計り知れません。
Q:借金をチャラにするのは、借りた先に悪く、後めたい気持ちがあります
法律上の制度や権利を行使しているだけです 消費者金融業者が一番嫌うことは、返済ができなくなった債務者が、返済や整理をせず放置することです。破産するのは、債権者のためでもあります。ぜひ、一歩を踏み出してください。
交通事故について
Q:保険会社との交渉を弁護士に頼むメリットがわかりません
保険会社は示談金をできるだけ抑えようとする傾向があります。一方で、弁護士は被害者の正当な損害賠償を求めて交渉します。弁護士に依頼することで、慰謝料や休業損害、後遺障害等級の適正な評価を得やすくなり、結果的に賠償額が大幅に増えるケースもあります。
Q:家族が交通事故で亡くなりました。この場合、どのように相談すれば良いのでしょうか?
ご遺族が相談者として、事故の状況や加害者の情報、保険の状況などを可能な範囲でご準備ください。突然のことで精神的にもご負担が大きいかと思いますが、弁護士が事実関係の整理や損害賠償請求の方法などを丁寧にご案内いたしますので、安心してご相談ください。
労働事件について
Q:残業代は過去どこまで遡って請求できるのでしょうか?
原則として、残業代の請求は「3年分」まで遡ることができます(2020年4月の法改正以降)。ただし、それ以前の残業については2年が適用される場合もあるため、早めにご相談いただくことが重要です。
Q:請求された残業代はすべて支払う必要はあるのでしょうか?
まずは、請求された内容が法的に正当かどうかを確認する必要があります。たとえば、労働時間の記録や就業規則、労使協定などをもとに、支払い義務があるかどうかを判断します。必要に応じて、交渉や紛争解決の手続きも弁護士が対応しますので、一度ご相談ください。